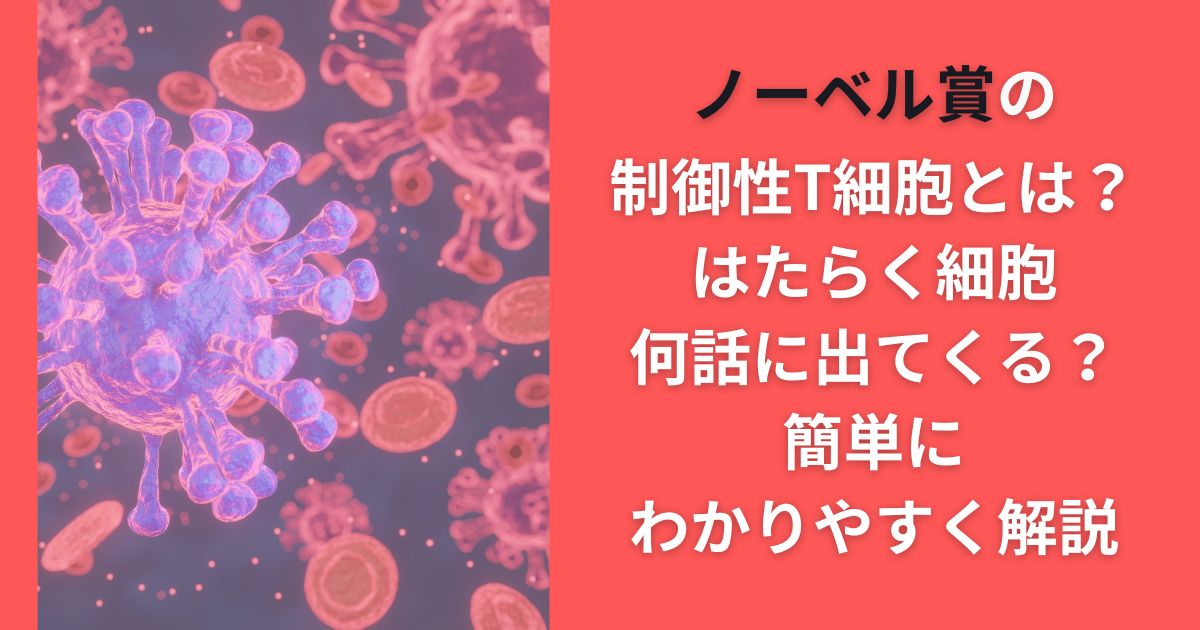今回の記事では、ノーベル生理学・医学賞受賞で一躍有名になった「制御性T細胞」について、詳しくリサーチしてまとめてみました。
私たちの体を守る免疫システムの「暴走」を防ぐ、非常に大切なブレーキ役なんですよ。
漫画『はたらく細胞』ではどんなキャラクターとして登場しているのでしょうか?
そしてその働きを坂口志文教授がどう解明したのか、簡単にわかりやすく解説していきますね。

この記事は、免疫学の基本的な知識をわかりやすく解説したものです。
より詳しく正確な情報については、医学の専門書や信頼できる学術情報源を調べてくださいね。
スポンサーリンク
ノーベル生理学・医学賞受賞!坂口志文教授の「制御性T細胞」とは?
2025年、日本の坂口志文大阪大栄誉教授らにノーベル賞が贈られるという嬉しいニュースが飛び込んできました。
その偉大な研究テーマこそが、この制御性T細胞です。
坂口教授は、免疫細胞が自分の体を攻撃しないように見張る、特別な細胞の存在を世界で初めて明らかにしたんです。
この発見は、免疫学に革命をもたらし、難病治療の扉を開いた大発見として評価されています。
坂口志文さん、不遇乗りこえノーベル賞に 妻・教子さんと続けた研究https://t.co/B2P4HIVWnA
— 朝日新聞デジタル速報席 (@asahicom) October 6, 2025
ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった坂口志文さんが見つけた、制御性T細胞。
坂口さんは30年以上前にその存在に気づきましたが、当時の常識を覆すその考えに、世界の研究者の目は冷ややかでした。… pic.twitter.com/YGHzXs0CWx
制御性T細胞の「末梢性免疫寛容」の発見が評価
坂口志文教授の制御性T細胞に関する研究が評価された最大の理由は、「自己寛容(じこかんよう)」という仕組みを解明した点にあります。
「免疫は外敵を攻撃するもの」という一方向の理解しかなかった免疫学に、「攻撃を抑えてバランスを保つ」という新しい概念をもたらしたそうなんです。
- 自己寛容:自分の免疫が、自分の体(自己)を攻撃しないようにコントロールされている状態です。
- 制御性T細胞は、この自己寛容を保つ「免疫の交通整理係」として働いています。
もしこの機能が破綻すると、ブレーキが効かなくなり、免疫細胞が自分の体を攻撃し始めてしまいます。
それが自己免疫疾患という病気になってしまうわけですね。
坂口教授らの発見は、この「免疫の暴走」を防ぐための重要なカギを見つけた功績なのです。
スポンサーリンク
「制御性T細胞」は漫画・アニメ「はたらく細胞」何話に出てくる?
専門的な話ばかりだと難しく感じてしまいますが、実は制御性T細胞は人気漫画・アニメ『はたらく細胞』でも大活躍していますよ!
この細胞がどのような姿で、どんな役割を担っているのか見ていきましょう。
登場キャラクターと登場回
『はたらく細胞』では、制御性T細胞はスーツ姿のクールで知的な女性として擬人化されています。
第1話から登場し、ヘルパーT細胞の秘書のような立ち位置でスーツ姿の女性として描かれています。
今年のノーベル生理学・医学賞の制御性T細胞は「はたらく細胞」でも出てくるのかなと思って調べたら、がっつり居て感心してる。だとすると今回のテーマは大人より子供の方が詳しいのかもしれない。 https://t.co/EReDIdWBFD pic.twitter.com/lVIRPRbNlp
— Zee a.k.a. Non (@ZeeThaBQF) October 6, 2025
| アニメ登場話数 | 漫画の巻数(目安) | 役割 |
| (1期)9話 「胸腺細胞」 | 3巻 | ヘルパーT細胞をやれやれと眺める姿で登場。 |
| (2期)7話 「がん細胞II(全編)」 | 5巻 | T細胞によるがん細胞への攻撃を抑制してしまう。 |
| (2期)8話 「がん細胞II(後編)」 | 5巻 | がん細胞を守ることをやめ、攻撃を許可する。 |
特にがん細胞との戦い(アニメ2期7話・8話)のエピソードは、ノーベル賞で評価された制御性T細胞の「ブレーキ」の重要性が最もよく理解できる回ですよ。
アニメ『はたらく細胞』で制御性T細胞について説明している話数リスト
— だしまきたまごPだったやつ (@DSMK_miyusuki) October 6, 2025
1期
9話:ヘルパーT細胞をやれやれと眺める制御性T細胞さん
2期(『はたらく細胞‼︎』)
7話:T細胞によるがん細胞への攻撃を抑制してしまう制御性T細胞さん
8話:がん細胞を守ることをやめた制御性T細胞さん
| スピンオフ作品 | 漫画の巻数(目安) |
| はたらく細胞BLACK | 8巻 第44話から第46話まで |

BLACKはスピンオフ漫画で作者さんが違うよ
キャラ設定も違う部分があるみたいだよ
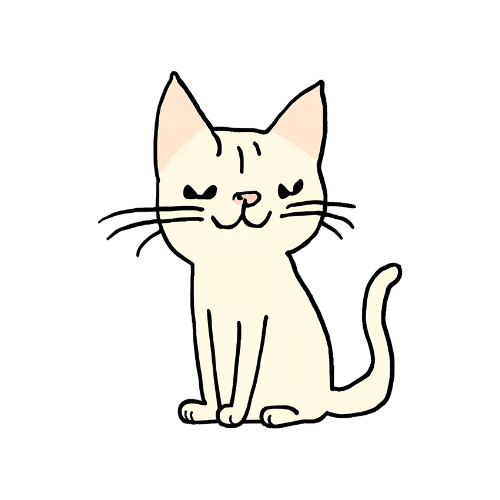
はたらく細胞BLACKの8巻の話。
— オメガ (@omegagpajt) October 13, 2024
キラーT細胞のすごさを知る。
キラーT細胞と
ナイーブT細胞(制御性T細胞)
の話で腎臓でB細胞を攻撃する
ところでキラーT細胞が
静止されたとき、
「本当にわからねぇ…。」と
言うじゃん。
スポンサーリンク
「制御性T細胞」を簡単にわかりやすく説明:AIに聞いてみた
制御性T細胞の働きが難しいので、AIに色々聞いてみました!
その結果を、小学生でもわかるように簡単な表現でまとめてみました。
一言でいうと、「体の平和を守るストップ役」です。
| イメージ | 制御性T細胞の働き |
| パトロール役 | 免疫細胞は、外から入ってきたバイキン(悪者)をやっつける「パトロール隊」です。 |
| 暴走の危険 | パトロール隊は悪者をやっつけようと興奮しすぎると、間違えて問題のない自分の体の中の細胞(一般市民)まで攻撃し始めそうになってしまいます。 これは大ピンチですよね! |
| ストップ役 | そこで登場するのが制御性T細胞です。 「みんな、落ち着いて!それは敵・悪者じゃないよ!」と大きな声でストップをかけます。 |
| 結果 | このストップ役のおかげで、パトロール隊は間違いを止め、体の中は平和に保たれるのです。 |
この細胞がいるからこそ、私たちは普段、アレルギーや原因不明の病気から体を守られているのですね。
スポンサーリンク
「制御性T細胞」はどんな病気に役立つの?
制御性T細胞の研究は、今、多くの難病の治療法開発に直結しています。
主に、免疫が強すぎるときと、免疫が弱すぎるときの、二つのパターンで応用が期待されています。
免疫が強すぎる病気への応用
ブレーキが壊れて免疫が暴走してしまう病気、つまり自己免疫疾患やアレルギーの治療に役立ちます。
制御性T細胞にしっかり「ストップ」をかけてもらう必要がある状態です。
自己免疫疾患などの一例
- 1型糖尿病:免疫が誤ってインスリンを作る膵臓の細胞を攻撃してしまいます。
- 関節リウマチ:免疫が関節を攻撃し、痛みや腫れを引き起こします。
これらの病気に対しては、制御性T細胞を患者さんの体内で増やしたり、活性化させたりして、「ブレーキ」の力を強める研究が進められています。
「特効薬」として期待されている分野です。
【ノーベル生理学・医学賞に坂口志文氏】
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) October 6, 2025
免疫暴走による病気止める「制御性T細胞」とはhttps://t.co/j59eRRFSNI
坂口志文・大阪大学特任教授が発見した「制御性T細胞」。免疫が自分の体を攻撃してしまう1型糖尿病などの自己免疫疾患の治療技術として有望です。#ノーベル賞 pic.twitter.com/TntdttrLge
免疫が弱すぎる病気(がん)への応用
逆に、がんのように本当は免疫が頑張ってやっつけてほしいときに、制御性T細胞が間違ってストップをかけて邪魔をしてしまうことがあります。
制御性T細胞は、「自分の細胞に対する攻撃はすべてストップする」というルールに忠実です。
がん細胞は、外から入ってきたバイキン(外敵)と違い、体の内側で増えた細胞。
- がん細胞:免疫から逃れるために、制御性T細胞を操り、味方にして、免疫にブレーキをかけさせます。
今年のノーベル医学・生理学賞の坂口教授は制御性T細胞を発見した人なんですね!
— 猛牛はなぴよ (@Gok87Z) October 6, 2025
「はたらく細胞」のおかげですごく身近に感じます。#ノーベル賞2025 pic.twitter.com/fI7pZhZFqP
この場合は、一時的に制御性T細胞の働きを弱める(司令を止める)ことで、免疫が、がん細胞を悪者としっかり認識でき、全力で攻撃できるようにする治療法が開発されています。
ノーベル賞を受賞した本庶佑教授のがん免疫療法の研究とも深く関わる、最先端の医療分野なんです。
こんなに強かったの!?「はたらく細胞!!」7話、“がん細胞”をかばう制御性T細胞に驚きの声続々 https://t.co/syKkFFW6Cy
— 和泉 (@48ePOIyYjPTH63o) January 29, 2024
この話を読めばターボ癌がなぜ起こるのかが理解できると思います。制御性T細胞誘導はリスクがあるのです。
スポンサーリンク
「制御性T細胞」に関するよくある質問(Q&A)まとめ
Q1. 制御性T細胞の「二面性」って何ですか?
A. 制御性T細胞は、「自分の体を守る」という良い面と、「がん細胞の味方をしてしまう*という悪い面(二面性)を持っています。
体の平和を守るために免疫を止めるのが本来の仕事ですが、このブレーキががん細胞によって悪用されてしまうことがあるんですね。
Q2. 「制御性T細胞」を増やすにはどうしたらいいですか?
A. 食事や運動で劇的に増やす方法はまだ確立されていません。
しかし、医療の分野では、患者さんの血液から制御性T細胞を取り出し、体外で増やしてから体内に戻す細胞治療の研究が進んでいます。
これは将来的に、アレルギー治療などで期待される方法です。
Q3. 「T細胞」と「制御性T細胞」は同じものですか?
A. T細胞という大きなグループの中に、攻撃役のキラーT細胞や、司令塔のヘルパーT細胞など、さまざまな種類があります。
制御性T細胞は、そのT細胞グループの中で「ブレーキ役」という特殊な役割を持っている、大切な一員です。
スポンサーリンク
まとめ
今回の記事では、ノーベル生理学・医学賞受賞というトピックをきっかけに、制御性T細胞について解説してきました。
まず、この細胞は坂口志文教授によって発見され、過剰な免疫反応を抑制する「ブレーキ役」として、ノーベル賞の受賞対象となりました。
また、『はたらく細胞』では、免疫の暴走を抑える重要なキャラクターとして描かれており、親しみやすい存在です。
そして、制御性T細胞は、自己免疫疾患やアレルギーなどの病気の治療に大きな希望をもたらす、未来の医療の鍵を握る細胞です。
この画期的な発見が、世界中の難病を克服する大きな一歩となることを期待しましょう!
スポンサーリンク
スポンサーリンク