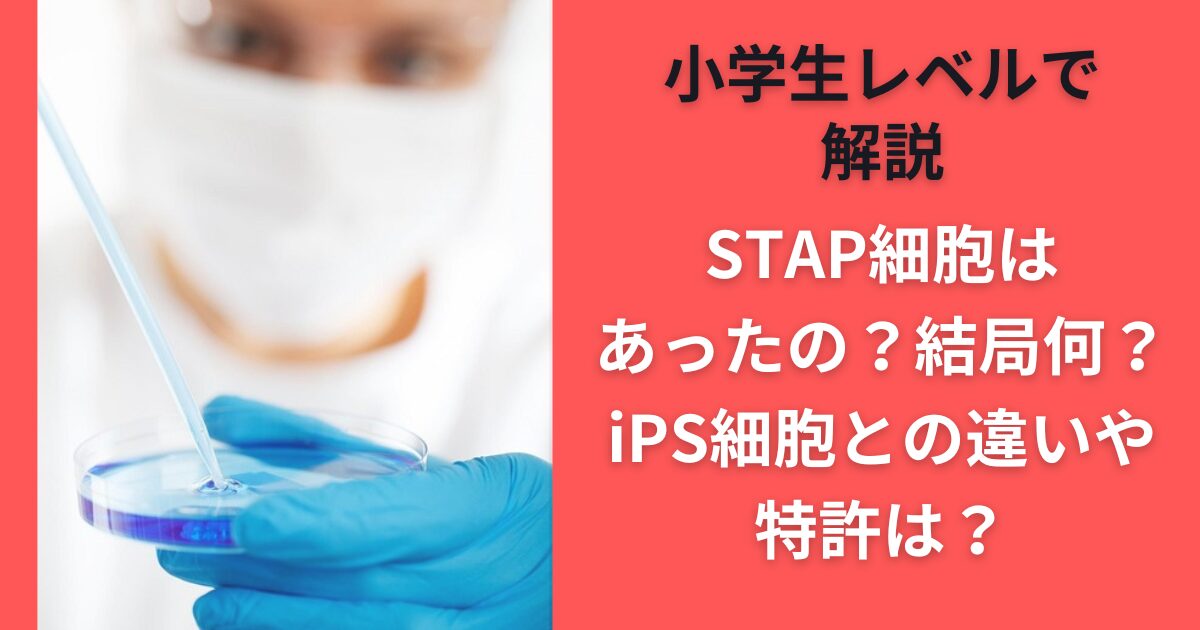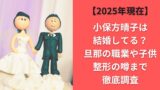「STAP細胞」って聞いたことありますか?
2014年に小保方晴子さん(おぼかたはるこ)が
理化学研究所(理研)で発表し、大騒ぎになったあの細胞です!
「結局なんだったの?」とモヤモヤしている人も多いはず。
そこで今回は、
AIに聞いて、小学生でもわかるように教えてもらいました。
STAP細胞はあったの?
結局どんな細胞?
iPS細胞との違いは?
特許ってどうなったの?など
分かりやすくまとめてみました。
ぜひ最後までお読みくださいね!
スポンサーリンク
STAP細胞はあったの?AIにわかりやすく説明してもらった
STAP細胞はなかった
結論:STAP細胞は「あった」とは認められていません。
まず一番気になるのは、
「STAP細胞って本当にあったの?」という疑問ですよね。
2014年に「すごい細胞ができた!」と世界中で話題になりました。
小保方晴子さんが
「すっぱい液に浸すだけで万能細胞が作れる!」と理研から発表しましたが、
その後いろんな研究者が同じように実験しても、再現できませんでした。
小保方晴子さんにあこがれて
— 勇者王ただし (@Manx_Missile_jp) April 8, 2024
割烹着着てた看護主任
元気にしてるかなあ pic.twitter.com/7h6EM93gIR
さらに、発表された論文に不正やミスがあったことがわかり、
STAP細胞の存在自体が否定されることになりました。
別の細胞が入っていた
理研の調査で
「STAP細胞はES細胞(胚性幹細胞)の混入だった」と判明し、
論文は撤回されました。
STAP細胞だと思っていたのは、他の違う細胞だった、ということなんです。
つまり、「STAP細胞はあります!」という言葉は有名になりましたが、
科学的には「なかった」とされています。
スポンサーリンク
STAP細胞って結局何だったの?簡単に説明
STAP細胞は変身できる細胞のはずだった
STAP細胞は、
正式には「刺激惹起性多能性獲得細胞
(しげきじゃっきせいたのうせいかくとくさいぼう)」といいます。
これは、普通の体の細胞に
ちょっとした刺激(たとえば、すっぱい液につけるなど)を与えるだけで、
赤ちゃんの細胞のように何にでもなれる細胞に変身する、というものでした。
具体的には、
細胞を「pH5.7の弱酸性液」に30分くらい浸すだけで、
どんな細胞にも変身できると言われました。
当時も云ったけど、小保方さんのSTAP細胞問題の論点は『細胞が存在したかどうか』ではなく、『彼女の論文に書かれた方法では作るコトが出来なかった』コトなんだよ。科学は再現性が重要で、論文の記述に沿って追実験を行った結果、誰も客観的な再現を示せなかったからダメだったって云うだけ。
— ハシモトケン (@hashiken0529) April 17, 2025
病気の治療に役立つはずだった
もし本当にできたら、
病気の治療や新しい薬の開発に役立つ
「夢の細胞」になるはずでした。
でも、実際にはその方法で万能細胞を作ることはできなかったのです。
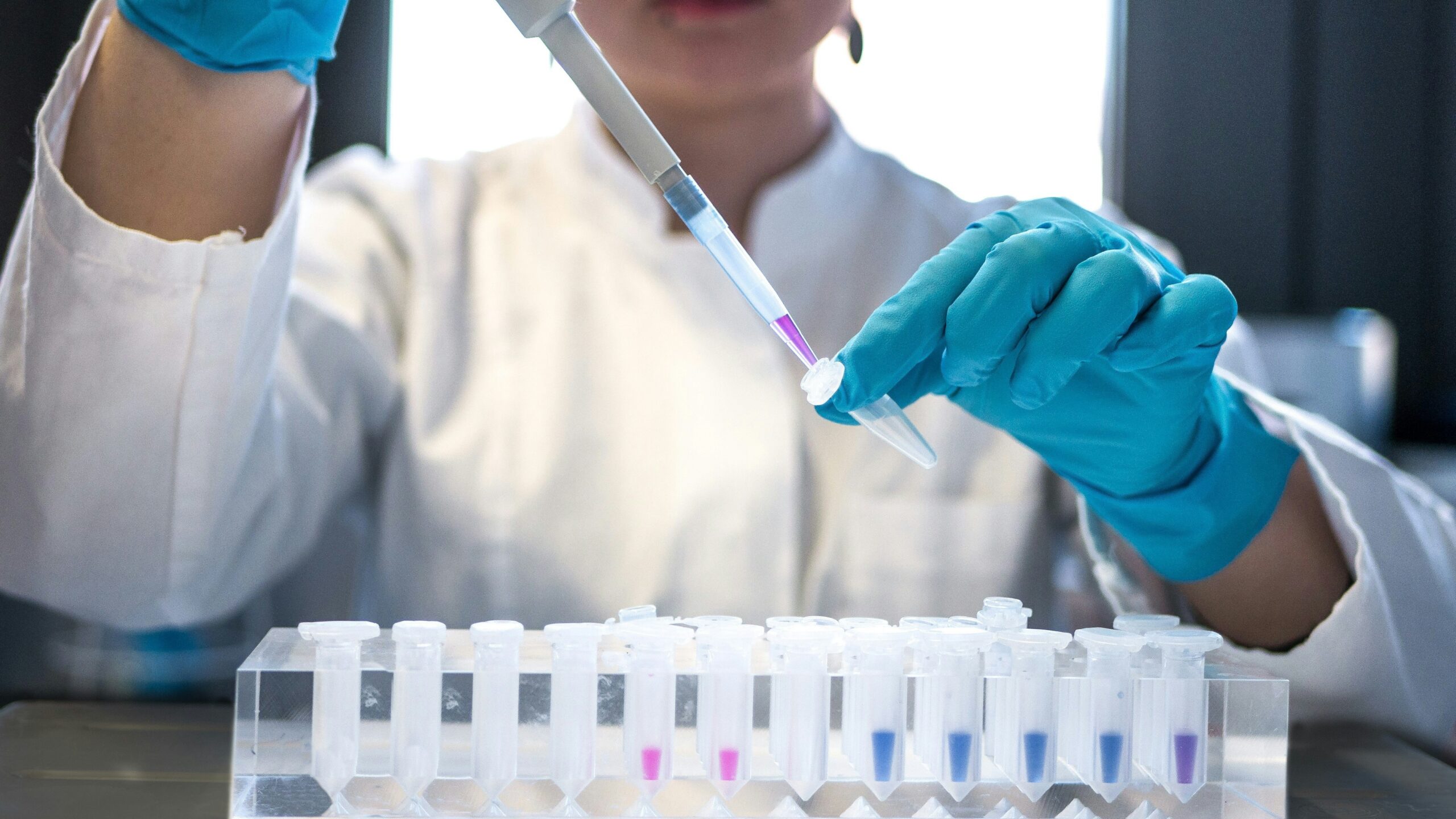
スポンサーリンク
STAP細胞とiPS細胞との違いは?小学生がわかるように解説
iPS細胞とは?
iPS細胞(アイピーエスさいぼう)は、
京都大学の山中伸弥教授が2006年に成功した細胞です。
皮ふなどの普通の細胞に
「特別な4つの遺伝子」を入れることで、
様々な働きのできる万能細胞に作り変えることができます。
この発見はとても画期的なものでした。
iPS細胞は、今でも再生医療や新しい薬の開発など、
いろいろな研究や治療に実際に使われています。
【治験結果】iPS細胞でパーキンソン病が改善か、脳に移植し6人中4人 京都大病院が発表https://t.co/9uvJ2ttpwy
— ライブドアニュース (@livedoornews) April 16, 2025
4人は症状や運動機能の改善がみられ、介助が不要になったり、一定期間車いすを使わずに生活できるようになったりする人もいたという。年度内にも製造販売について承認申請する見通し。 pic.twitter.com/JotBT1eS9U
iPS細胞で山中教授はノーベル賞受賞
この発見で山中教授は2012年にノーベル賞を受賞しました。
iPS細胞は「確実に作れる方法」として世界中で認められました。
例えば、
目の病気やパーキンソン病、心臓病の治療研究に活用され、
実際に、患者さんにこの細胞を使った治療が始まっています。
\📺メディア情報📢/
— iPS細胞研究所 (@CiRA_KU_J) October 2, 2024
明日朝のNHK「おはよう日本」に #山中伸弥 教授がVTR出演します!
来週からノーベルウィークというこで、山中教授がノーベル賞を受賞して12年経ち、iPS細胞研究がどのぐらい進んでいるかなどをお話しました。
NHKの #首藤奈知子 アナウンサーにインタビューしていただきました! pic.twitter.com/5d570GifXb
STAP細胞とiPS細胞との違い
STAP細胞は「簡単にできる」と言われていましたが、
結局うまくいきませんでした。
iPS細胞は「ちょっと難しいけど本当にできる」細胞として、
今も世界中で研究・利用されています。
| 項目 | STAP細胞 | iPS細胞 |
|---|---|---|
| 作り方 | 弱い酸に浸して培養 | 遺伝子を人工的に挿入する |
| 時間 | 30分~数日 | 数週間~数ヶ月 |
| 再現性 | 誰も成功しなかった | 世界中の研究室で再現可能 |
| 実用化 | なし | 治療・研究に使用中 |
| ノーベル賞 | なし | 2012年山中伸弥教授が受賞 |
スポンサーリンク
STAP細胞の特許はどうなった?ハーバード大学が取得?
STAP細胞の特許が10年越しにやっと認定!?
実は、STAP細胞の作り方に関する特許が
2024年4月23日、アメリカで正式に認められました。
この特許は
「Generating pluripotent cells de novo(新しい多能性細胞の生成)」というタイトルで登録され、
特許番号は「11,963,977」です。
つまり、
「STAP細胞の技術」が“発明”として
アメリカで認められたことになります。
ただし、これは「方法のアイデア」が
認められただけにすぎません。
STAP細胞はある!というポストには必ずコミュニティノートが付くので正式な特許情報を。
— aki (@1x_aki) March 24, 2025
STAP細胞(刺激惹起性多能性獲得細胞)の特許が2024.4.23に米国で成立。VCELLTHERAPEUTICS, INC.という企業が最終的な権利者となっています。特許番号は11,963,977 (Patent # 11,963,977 issued April 23, 2024)
STAP細胞の特許を取得したのはハーバード大学?病院?
最終的にSTAP細胞の特許を取得したのは
ハーバード大学でも関連病院でもありませんでした。
もともと、
STAP細胞の特許は
理化学研究所やハーバード大学、
関連病院のハーバード大学附属の
ブリガム・アンド・ウィメンズ病院などが出願していました。
しかし、長い審査や権利の移動があり、
最終的には「VCELL THERAPEUTICS, INC.」という
アメリカの企業が特許の権利者となっています。
そのため、
ハーバード大学が直接持っているわけではありません。
この会社は再生医療の特許を100件以上保有しており、
STAP細胞関連の権利を管理しています。

STAP細胞の特許取得:アメリカの会社「VCELL THERAPEUTICS, INC.」
VCELL社は「特許ビジネス」を専門とする企業で、
STAP細胞の技術を利用して新しい治療法を開発しようとしています。
STAP細胞の技術が実用化されれば、
ライセンス収入を得られる可能性があります。

ライセンス収入って?
他の会社がその技術を使いたいとき、
VCELL社にお金を払うってことだね
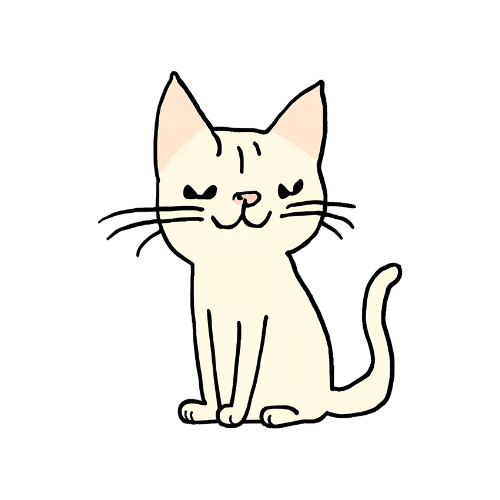
ただし、
現時点ではSTAP細胞の再現性が確認されていないため、
実用化のめどは立っていません。
スポンサーリンク
ハーバード大学が関係していたのはなぜ?小保方さんの師匠がいたから!
チャールズ・バカンティ教授がいたから
ハーバード大学がSTAP細胞の研究に関わっていたのは
「チャールズ・バカンティ教授(Charles Vacanti」という
有名な先生がいたからです。
バカンティ教授は、
再生医療や組織工学という分野で、
とても有名な研究者です。
小保方さん、ボストンに戻ってきて…STAP細胞の論文問題について、責任著者の一人米ハーバード大のチャールズ・バカンティ教授が15日、京都市で開かれた国際会議で基調講演した。教授は「STAP細胞はある」と強調したという。田口聖竜合掌 pic.twitter.com/IRvocPuaUw
— 田口 聖竜 (@seiryukarate) April 16, 2014
小保方晴子さんは、
理化学研究所(理研)で研究する前に、
ハーバード大学医学部のバカンティ教授の研究室で学んでいました。
STAP細胞を作るアイデアを研究
バカンティ教授は「刺激を与えるだけで細胞が赤ちゃんのように戻る」という
アイデア(STAP細胞のもとになる考え)を早くから持っていて、
小保方さんと一緒にその研究を進めていました。
だから、ハーバード大学がSTAP細胞の研究や特許に関わっていたのは、
バカンティ教授が小保方さんの指導者であり、
一緒に研究をしていたからなんです。
STAP細胞「再現簡単…は重大な間違い」論文共著者が見解。STAP細胞が簡単に作製できるとしたのは「重大な間違い」だったとする文書が、STAP論文共著者で米ハーバード大のチャールズ・バカンティ教授の研究室ホームページに(*´∀`)ノ
— ひろぽん暑いの苦手 (@hirokun_zz) September 14, 2014
スポンサーリンク
STAP細胞の特許成立って、結局STAP細胞は「あります」ってこと?
結論:STAP細胞は「あります」ということではない
ここがとても大切なポイントです!
必ずしもSTAP細胞が実際に存在することを意味するわけではありません。
STAP細胞の特許が成立したことは、
特許が「新しいアイデアや方法」に対して与えられるものであるため、
実際にその技術が動くかどうかは別問題です。
アレ?今になって小保方さんがトレンド入り。『STAP細胞はあります。』当時は捏造と叩かれましたが、本当にSTAP細胞はなかったのか?のちにハーバード大学が特許を取ったものの、STAP細胞が作れる、ということではなかったようだ。特許というのは技術的可能性を認めるもので、科学的な再現性を pic.twitter.com/F1xvqipHuM
— ココナッツウォーター (@coconuts_water) April 17, 2025
作り方のアイデア・方法が評価されただけ
STAP細胞の特許も、
「こういう方法で細胞を作る」というアイデアや手順が認められたというだけで、
「STAP細胞が本当にできた」
「存在が証明された」ということにはなりません。
スポンサーリンク
まとめ
STAP細胞は一時「夢の細胞」として話題になりましたが、
今は科学的に存在しないと考えられています。
一方で、iPS細胞は本当に作られ、医療や研究で活躍しています。
STAP細胞の特許は2024年にアメリカで認められましたが、
これは「アイデアが認められた」だけで、
STAP細胞の存在や実用化を意味するものではありません。
科学の世界では、再現性や確かな証拠がとても大切なんですね!
まとめ比較表
| 項目 | STAP細胞 | iPS細胞 |
|---|---|---|
| 作り方 | 酸性の液体に浸す | 特別な遺伝子を細胞に入れる |
| 本当にできた? | できなかった(再現できなかった) | 世界中で成功し、実際に使われている |
| 特許 | 2024年に米国で認定(VCELL社が権利者) | すでに多くの特許が取得されている |
| 使われ方 | 実用化されていない | 医療や研究で使われている |
| ノーベル賞 | なし | 2012年に山中教授が受賞 |
関連記事
スポンサーリンク
スポンサーリンク